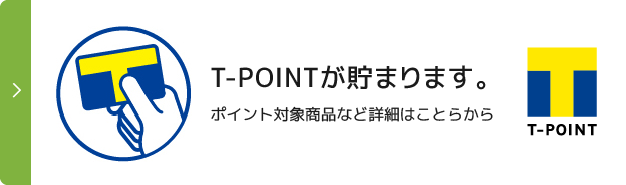コラム
短頭種気道症候群について
「短頭種気道症候群」とは鼻が短い犬種に多い、生まれつき気道の狭さが原因で呼吸がしづらくなる病気の総称です。代表種は主にパグやフレンチブルドック、シーズー、ボストンテリア、ブルドックなどが挙げられます。

この「短頭種気道症候群」に含まれる主な病気は、
・鼻の穴が狭い状態を指す「外鼻孔狭窄」
・喉の奥にある軟口蓋という、食べ物が鼻に逆流するのを防ぐ柔らかい膜状の組織が正常より長く垂れ下がってしまい気道を塞いでしまう「軟口蓋過長症」
・気管が生まれつき狭い状態の「気管低形成」
等が主に挙げられます。
上記の疾患を持つ子でよく見られる症状はいびきや呼吸音が大きい、呼吸が苦しくなる様子が多く見られ、その影響から体温調節が困難で熱中症になりやすい、嘔吐や吐き戻し等の症状が出る場合もあります。
このような症状を何年も放置してしまうと様々な病気の合併症を引き起こし、最悪突然死してしまうこともあります。
治療方法は生活習慣の改善や内科治療・外科治療を適切に組み合わせ、症状の緩和や進行を遅らせることが主に挙げられます。
生活習慣の改善は、短頭種は体温が上がりやすい傾向にある為、室温を低めに設定し体に熱がこもりにくくする事が大切です。
また日中の暑い時間に外出しない事、肥満な子は厚い脂肪で気道を圧迫しまう為太らせない事も重要です。食べる事が大好きな短頭種ですが、少し痩せ気味に管理することで呼吸の確保がしやすくなります。
外科治療はいくつか種類がありますが、よく行われる手術をご紹介します。
まず外鼻孔狭窄症の改善を目的とした手術で、鼻の出入口を一部切開し、鼻の穴を広げる事で呼吸確保に繋げます。
この他に軟口蓋過長症の改善には、軟口蓋を切除し空気の通りを改善し呼吸状態緩和に繋げる手術を行います。
内科治療ではステロイドや鎮静剤を投与する事が多いです。
また緊急時には酸素室での管理も挙げられ、ご自宅に酸素室を設置して頂くケースもあります。ただし、内科は一時的対応のみで、根本治療ではありません。
根本治療を考えるのであれば、外科治療が優先されると言えますが、麻酔下での手術は他の犬種に比べ、麻酔から目覚める際に呼吸困難の可能性が高く、そのリスクも踏まえて考える必要があります。
短頭種はとても可愛く魅力的な犬種であると同時に呼吸器疾患が多い犬種です。その為飼い主さんがしっかりと把握し、気になることがあれば早期の受診をお勧めします。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。